 「最高のチーム」というタイトルの記事を読んで、チームを組むことが最高の人生なのか、それともどんなチームでもそこにいる人々が最高であるべきなのかを考えていた智之介は、ふと目の前の人影に目が行く。
「最高のチーム」というタイトルの記事を読んで、チームを組むことが最高の人生なのか、それともどんなチームでもそこにいる人々が最高であるべきなのかを考えていた智之介は、ふと目の前の人影に目が行く。「こんばんは、智之介さん。今日も会議お疲れ様です」
顔にはにっこりと笑みを浮かべた、彼の最高のパートナー、桜子が立っていた。彼女はいつものように、メモ帳とノートパソコンを片手に、やる気満々で冷たい机の前に座り込んでいる彼を見つけて、接近してきたのだった。
「ねえ、智之介さん、ちょっと聞いてもらえますか? 私、最近すごく凝っているチーム物語を書いているんです。普段はラブロマンスとか書いていますが、今回はミステリー要素のあるものを目指しています」
「チーム物語? それって、私たちのことをネタにしたものなの? 桜子、やるな」
智之介はかばい笑いをしながら、彼女が出した最新作の原稿用紙を手に取る。
「『最高の仲間たち』…って、こ、これは…」
智之介の目から、もう一人のパートナーである重吾が飛び出してくる。しかも、その描写がなんとも繊細で、かつロマンティックなのだ。
「すごいね、桜子。智之介も重吾も、こんなに素敵に描かれているなんて」
桜子はにっこりと笑みを浮かべ、胸を張って言った。
「でも、それってどういうことですか? まさか、私たちが殺人事件に巻き込まれるとかになるんじゃないですよね?」
智之介が言うと、桜子はにやりと笑う。
「殺人事件はもちろんないですよ。ただ、チーム物語なら、ちゃんとストーリーに盛り込まないといけないですもんね」
桜子の狙いは、最高のチームがどうやって作られ、どうやって成長していくのかを描くことだった。智之介と重吾の協力を得ながら、次第にその野心が形になっていく。
さらに名前がついたメンバーたちも登場して、彼らが個々に抱く切実な思いを織り交ぜながら、桜子はどんどん物語を進めていく。
最後には、チームの団結力が試される場面が訪れる。事件はないが、いつ本当の危機が来るかわからない、緊張感あふれるシーンだった。
そして、果たして智之介たちのチームは、最高と呼ぶに相応しいチームとなった。
「桜子、すごいよ。最高のチーム物語を書いたね。そして、私たちがその中で最高のメンバーに選ばれたときの、あの緊張感や感動が、まさに最高って感じだ」
「そうですね。智之介さんたちは、完璧な人間関係を築いている最高のチームなんだと思いました」
桜子が言うと、智之介たちはうなずきあった。
彼らが最高のチームであることは、彼ら自身も認めることだった。
■この小説のちくわ様自己採点 感動的:9 笑える:1 悲しい:0 夢がある:10 怖さ:0. 合計点:20

最高のチーム|twitterトレンド
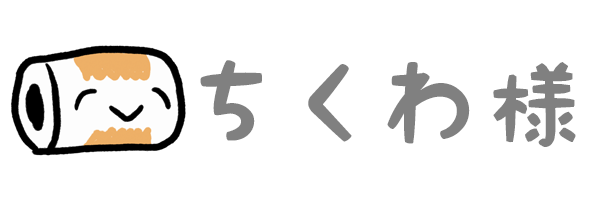



コメント